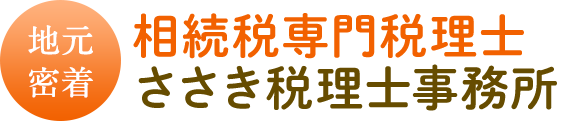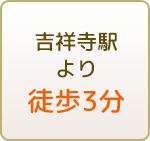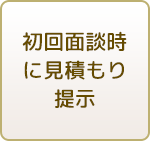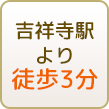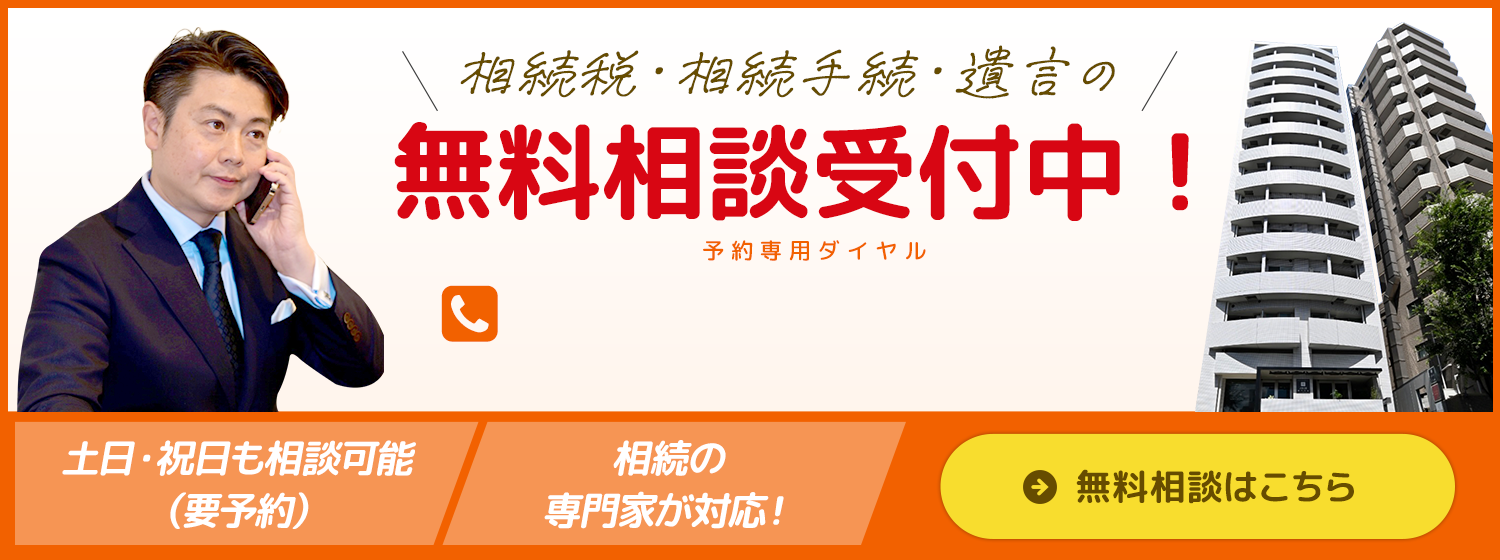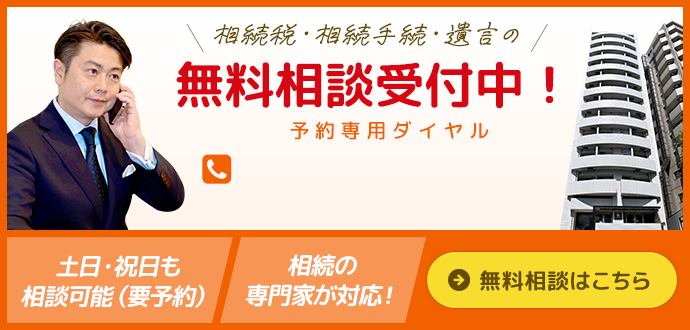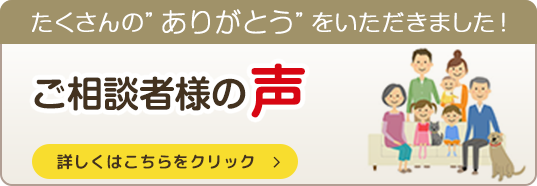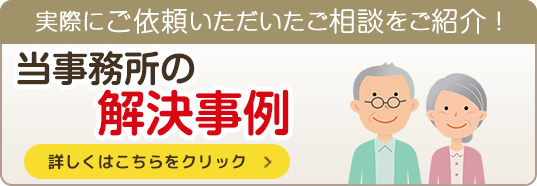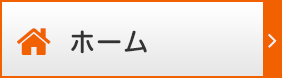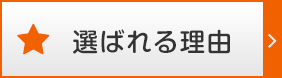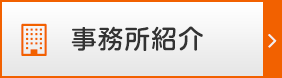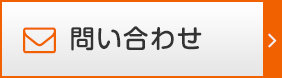相続税対策
安全に相続税を節税する対策については、大きく分けて2つの柱があります。
1つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策になります。
2つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。
もちろん、他にも方法はありますが、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあるため、その都度ご紹介したいと思います。
目次
生前贈与(暦年贈与)によって相続税を節税する
他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らしていこうと考えていく方法です。
これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減るというものです。
子供に毎年資産を贈与し、その資金で子供を契約者、親を被保険者とする生命保険を契約することで、親の死亡時に保険金としてまとまったお金が入り、納税資金を準備することができます。
また、贈与した資金の使用目的が決まっているため、浪費してしまうなど子供の金銭感覚を狂わせてしまう心配もありません。
そのためには税務署に「贈与事実」の心証が得られるものを確実に残しておくことに注意しましょう。
・毎年、「贈与契約書」を作成し、保存する
・110万円以上の贈与をして、毎年申告書を提出し、納税する
・贈与税申告書を保存する
・贈与者は生命保険料控除を活用しない
・その他、贈与の事実を認定できるもの
受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、通帳・印鑑の保管は受贈者がする以上のほかにも、ケースによって注意することがありますので、活用については生命保険会社などにご相談下さい。
※なお、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれるため、節税効果はありません。
生命保険を使って納税金を準備する
これは納めるべき相続税を確保していこうと考えていく対策です。
相続税を不動産などの資産を処分せずに一括で現金で支払えるように、生命保険金を利用して納税のための資金を準備できるようにするのが、このタイプの対策です。
具体的には、被相続人の加入している生命保険の受取人を相続人にしておけば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。
さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。
保険金受取人および被保険者を相続人として、保険契約者を被相続人とする契約であれば、相続が開始したときに生命保険契約に関する権利を相続人が引き継ぐことになります。
生命保険契約に関する権利については、相続開始のときに契約を解約するとした場合に支払われる解約返戻金の額によって評価されます。
解約返戻金のないものは評価されません。
なお、その権利自体は相続人が引き継いでいくことになりますが、解約返戻金相当額が振込保険料相当額より少ない場合には、相続財産の評価が下がることになります。
その他の相続税対策
①生前贈与(一括贈与の特例)をする
生前贈与は上記の「暦年贈与」の他、「一括贈与」の特例もあり、贈与税の計算方法が異なります。
暦年贈与
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除額(年110万円)を利用した贈与方法です。1年間の贈与額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。基礎控除額の範囲内で贈与を続けることで、贈与税を負担することなく配偶者や子どもに財産を渡せます。
ただし、毎年一定額の贈与を長く続けると「定期金給付契約」とみなされ、贈与税がかかる恐れがあります。また、被相続人の死亡3年以内に行われた暦年贈与は、相続税の課税対象になるので注意しましょう。
なお、2023年(令和5年)度税制改正大綱において、暦年贈与の税制見直しが盛り込まれました。2024年(令和6年)1月1日以後は、被相続人の死亡7年以内に行われた暦年贈与が相続税の課税対象となる見通しです。
一括贈与(贈与税の特例)
一度にまとまった財産を贈与する際は、一定の要件を満たすと以下の特例を利用できます。
●住宅取得等資金の非課税
●教育資金の一括贈与の非課税
●結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
両親や祖父母から住宅取得資金として贈与を受ける場合は、1,000万円まで贈与税が非課税になります。教育資金は1,500万円まで、結婚・子育て資金は1,000万円まで贈与税がかかりません。
上記の特例を利用する場合は、必要書類の準備や贈与税の申告、金融機関との資金管理契約などが必要です。
暦年贈与と同じく、一括贈与も2023年(令和5年)度税制改正大綱で今後の方針が示されました。「教育資金」「結婚・子育て資金」は適用期限の延長が盛り込まれています。一方、「住宅取得等資金」については、2023年(令和5年)12月31日で制度終了でしたが、延長が検討されています。
②不動産評価を活用する
不動産は、預貯金とは相続財産の評価方法が異なります。不動産をうまく活用すると評価額が下がるため、相続税の節税が可能です。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、土地の相続税評価額を80%減額できる特例です。被相続人が住んでいた土地を相続する場合、一定の要件を満たすと、330㎡を限度に評価額が80%減額されます。減額前の土地の評価額が4,000万円であれば、相続税評価額を800万円に下げることが可能です。
本特例は、被相続人の配偶者や同居親族などが適用対象です。利用できるか判断できない場合は、税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。
マンション・アパート経営
マンション・アパート経営も、相続税の節税対策になります。賃貸マンション・アパートは賃貸割合などを考慮して評価するため、住宅よりも評価額が下がるのが一般的です。賃貸用の土地・建物の評価額は、以下の算式で計算します。
●土地(貸家建付地):自用地の評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
●建物(貸家の家屋):固定資産税評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)
賃貸マンション・アパートは、一定の要件を満たすと「小規模宅地等の特例」も利用可能です。特例が適用されると、200㎡を限度に評価額が50%減額されます。
ただし、過度な節税は税務署から否認されるリスクがあるため、税理士などに相談したうえで賃貸経営を行うか検討しましょう。
③死亡退職金の非課税枠を使う
被相続人が亡くなり、相続人が勤務先から受け取る死亡退職金は相続税の課税対象です。ただし、死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。受取金額が非課税枠の範囲内であれば、相続税はかかりません。
小規模企業の経営者や個人事業主が加入する「小規模企業共済」の共済金も、相続税法上の死亡退職金に含まれます。経営者や個人事業主は、小規模企業共済をうまく活用すれば相続税の節税が可能です。
④養子縁組で基礎控除額を増やす
養子縁組とは、血縁関係のない人と法律上の親子関係をつくる公的な制度です。養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2つがあります。
●普通養子縁組:実親との親子関係を存続したまま養親と親子関係を結ぶ
●特別養子縁組:実親との親子関係を解消して養親と親子関係を結ぶ
養子縁組をすれば、子ども(法定相続人)の数が増えます。その結果、基礎控除額や死亡保険金の非課税枠も増えるので、相続税の節税につながります。
ただし、法定相続人に含める養子の数には制限があるので要注意です。被相続人に実子がいる場合は「1人まで」、実子がいない場合は「2人まで」となります。
⑤墓地や仏具などを生前に買って相続財産を減らす
墓地や仏壇、仏具といった祭祀財産には、相続税がかかりません。生きている間に墓地や仏具を買っておけば、そのぶん、相続税を抑えられます。
気をつけるべきポイントとしては祭祀財産が礼拝用ではなく、投資目的だった場合は相続税がかかるということです。また購入する際にローンを組んでも債務控除とはなりません。
⑥配偶者に居住用不動産を贈与する
20年以上連れ添った配偶者に自宅や居住用物件の購入資金を贈与すると、2000万円まで贈与税がかかりません。この制度で自宅の一部を妻や夫に生前贈与すれば、相続財産を減らせます。
ただ実際には配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使ったほうが、節税効果は高くなります。また不動産取得税などのコストがかかります。
⑦不動産を所有する法人を設立する
相続人が出資して不動産を所有する法人を設立し、手持ちの不動産をその法人に売却してしまうことで、相続そのものが不要になります。
売却した代金については、他の対策に使用すればよいですし、自宅などはその法人に賃料を支払うことで財産を減らすことができます。
出資した相続人は役員として報酬を得ることで出資額を回収でき、今後は相続が発生しないため、二次相続対策にも利用できます。
⑧相続手続・遺言執行費用を前払いする
相続の手続きや遺言の執行について、税理士などに依頼する場合は費用がかかりますが、その一部を生前に前払いしておくことで、財産を減らすことができるため、相続税対策になります。
相続手続や遺言執行の費用は相続財産から控除することはできないため、相続人にとっても出費が抑えられるメリットがあります。
⑨家族信託を行う
相続税の対策は、生前贈与など長い期間をかけて効果を高めるものもあります。ところが、被相続人が認知症などで法的な判断ができなくなってしまうと、それ以降すべての対策ができなくなってしまいます。
そのため、あらかじめ家族信託を行って財産の全部や一部について信託財産としておくことで、安全に相続税対策が行うことができ、結果的に大きな効果を生むことになります。
⑩不動産の組み替えを行う
現在所有している土地が狭小であったり、形状が悪かったり、不便な場所であったりする場合は、将来売買や賃貸のしやすい土地や資産価値の高いマンションなどに買い替えておくことで、他の相続税対策が行いやすくなりますので、不動産の組み替えを行うことも有効となります。
⑪分筆を行う
少し特殊な方法ですが、現在の土地が角地などで評価が高い場合、分筆を行うことで角地ではない土地を発生させることで、全体の評価額を下げることができます。
大きな土地の場合、複数の相続人が分筆した土地をそれぞれ相続する場合などに有効な相続税対策となります。
⑫不動産投資を行う
相続税の対策において、不動産を活用することでさまざまなメリットを受けることができます。
まず、単純に土地を購入した場合、相続財産の価値を計算する際の評価額は、相続税路線価や固定資産税評価額のいずれかになり、時価(実勢価格)の7~8割が目安になっています(逆に高い場合もあります)。
また、建物の固定資産評価額は取得価額の約60%(建物によって異なる)となりますので、建物を建てることで評価額を下げることができます。
さらに、購入した土地にアパートなどを建てた場合は、貸家建付地と呼ばれ、下記の通り、土地建物それぞれに評価額を下げることができ、大きな相続税対策になります。
土地:借地権と貸家権割合で評価額を9~27%下げて、73~91%の評価額
建物:30%の借家権割合を減額できるので、約60%の固定資産税評価額と併せて約42%の評価額
過度な相続税対策は、課税庁に否認されるリスクが格段に上昇します。自分の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極めて、実行していただきたいと思います。