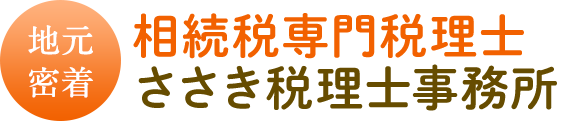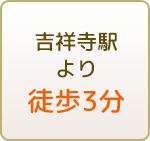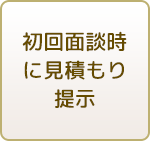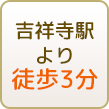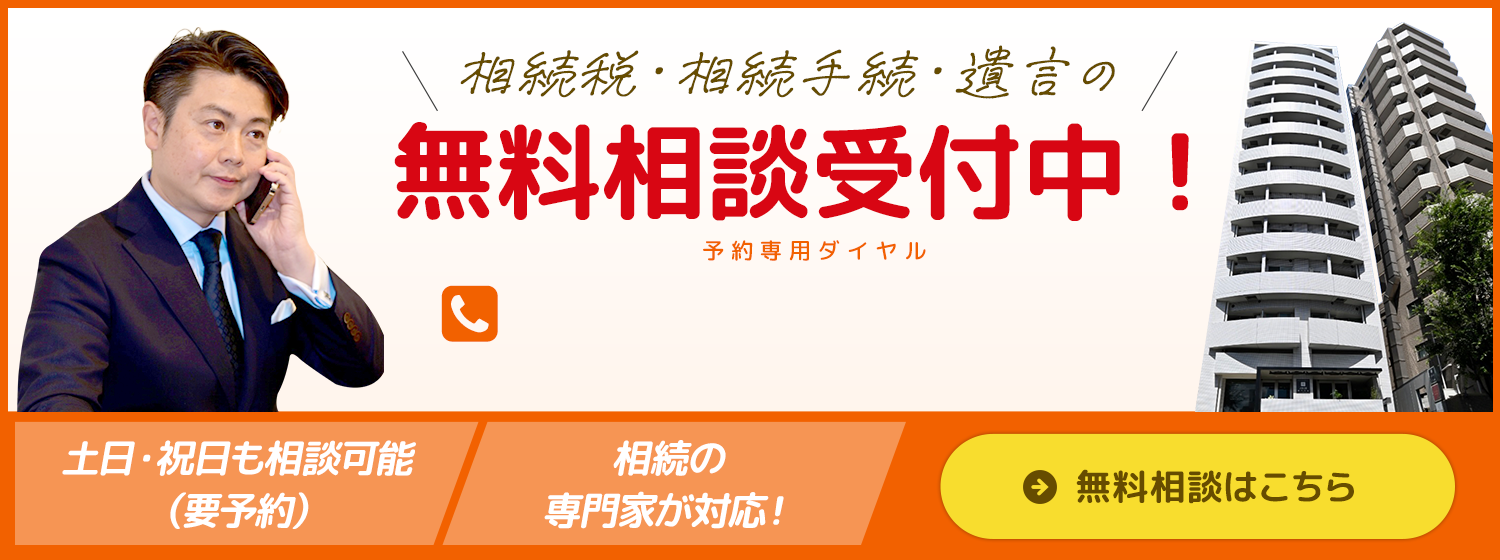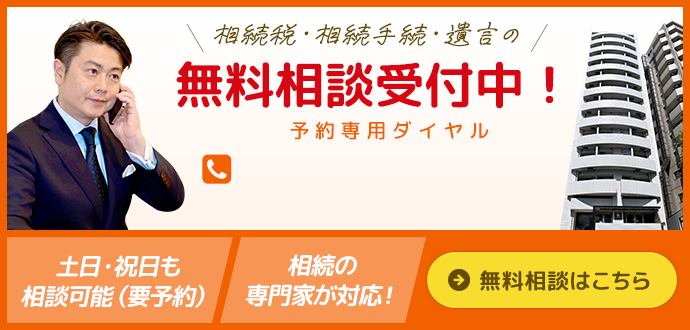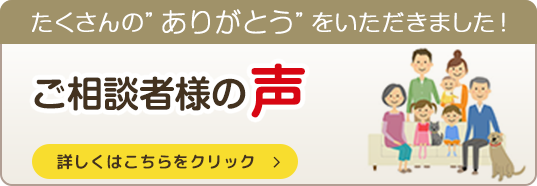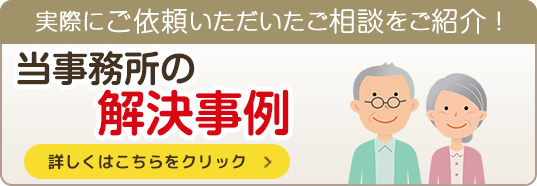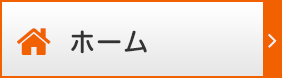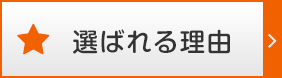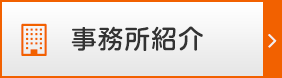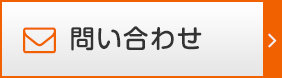養子は相続人になる?
養子は実の子供(嫡出子)と同じとみなされるので、相続人となります。
養子になったからといって、実の父母との関係が変わることもないため、実親の相続人にもなります。
養子になることにより、実親と養親の両方から相続できるようになりますが、実親との親族関係が終わっている場合など、条件によっては、異なりますので専門家に相談し、必ず確認しましょう。
養子の2つの形態
養子縁組には、特別養子縁組と普通養子縁組の2つの形態があります。
特別養子縁組は、養子となった者と実親との親子関係が法律上消滅する為、養子になった方は実親の相続人になることができません。
一方で、普通養子縁組は、養子先の親と法律上の親子関係が生じ、かつ、実親との親子関係が継続します。
つまり、養子になった者は養子先の親と実親の2組の親の子となり相続人となります。
養子縁組と養子人数の制限
養子人数については、民法上は何人いても問題ないですが、一方で相続税法上においては、課税を公平に行う為に法定相続人の養子数に下記のような制限があります。
1.養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、1人まで
2.養親に実子がいない場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、2人まで
※実子との親子関係が消滅した特別養子縁組の場合や連れ子で養子の場合は、この養子人数制限の対象にはなりません。
養子の人数が制限され影響が出るのは、下記の3つの人数です。
1.相続税の基礎控除に関わる法定相続人の人数
2.相続税の総算出額に関わる法定相続人の人数
3.生命保険金や死亡退職金の相続税非課税枠に関する法定相続人の人数
養子縁組を無制限に認めれば、法定相続人の人数を相続税逃れのために悪用される可能性があり、この相続税課税回避行為を未然に防がなければならないため、相続税法上の養子の人数が制限されているのです。
この記事を担当した執筆者

武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター
税理士・行政書士
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
- 遺産整理業務の内容と流れ
- 相続手続きでつまづくポイントとは?専門家が解説
- 複雑な相続手続き
- 相続人が多くて話がまとまらない場合
- 面識のない相続人がいる場合
- 相続人が未成年の場合
- 海外に在住している相続人がいる場合
- 相続人が行方不明の場合
- 相続人が認知症の場合
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議の種類
- 遺産分割協議の注意点
- 遺産分割協議書の作り方
- 遺産分割の調停と審判
- 遺産分割協議のQ&A
- 遺産分割協議の失敗事例
- 相続に関わる手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求
- 預貯金の名義変更
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
- 相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは
- 相続の基礎知識
- 法定相続と相続人
- 相続人は誰になるのか
- 養子は相続人になる?
- 前夫が亡くなった時の相続人は?
- 前妻との間に生まれた子供も相続人になる?
- 遺産の分類と相続方法
- 相続手続に必要なもの
- 戸籍収集はこんなに大変!